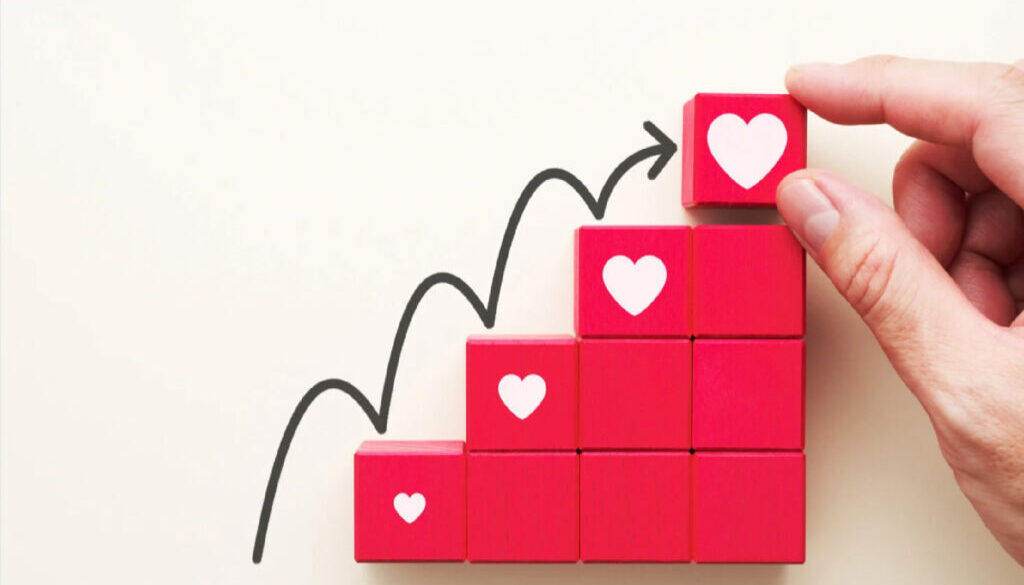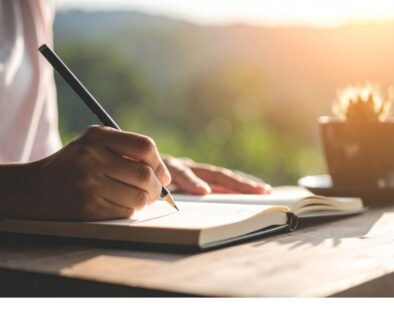親元を離れてグループホームで過ごす目的とは?
●自分に都合のいい状況を重視しがち
障がいのある人のなかには、日常生活で、
自分から身の回りのことをしようとしない人も、よく見られます。
グループホームに入ってから知的障がいの診断を受けた50代の男性は、
身の回りのことをしようと思えばできるのですが、
その意欲がありませんでした。
1週間以上、入浴をしなくても平気です。
声をかけられなければ洗濯もしない、
着替えや掃除も自分からすることはない状況でした。
この人の場合は、
「お風呂は2日に一度は入りましょう。洗濯は1週間に一度、
この曜日に行いましょう、掃除もこの曜日に一緒にしましょう」
という形で、まずタイミングを決めました。
そして、そのタイミングになったら声をかけます。
その際、
「どうします? しますか?」
ではなく、
「今日は決めた日なので、やりましょう。では、やってくださいね」
というアプローチを繰り返したのです。
最初のうちは、
「今日はいいです…」
と拒否することもありましたが、続けるうちに、
まだ自発的に行うには至らないまでも、
声をかけられればすんなりとできるようになりました。
拒否をせずできるようになるまでは、
半年以上はかかったと記憶しています。
●障がいのある人は、じつは人をよく見極めている
はじめは、断るタイミングや理由を探していたようにも見えました。
さらに、
「いや、いいです」
と言えばすぐに引いてくれるスタッフに対しては、
かならず断っていたのです。
彼らは、相手の性格などを意外にもよく見抜く力を持っています。
スタッフが一度断っても引かない場合、
彼らは重い腰を上げて行動し始める傾向がよく見られます。
自分にとって都合のよい状況をつくるために人を見極めることは、
多くの発達障がいを持つ人に共通する特徴のように思うのです。
●できないことも時間をかけて取り組んでいく
入居者全般に共通して言えるのは、
「急に変わることはない」ということです。
「こういうふうにやってください」
とお願いして、すぐに指示通りに行動する人であれば、
そもそもグループホームには入る必要がなかったでしょう。
ですから、とにかく時間をかけて、
じっくりと一緒に取り組むしかありません。
半年、または1年かけて、
ひとつのことがやっとできるようになるくらいのペースで、
考えるべきではないでしょうか。
●グループホームだからこそできることがある
グループホームに住む人々のひとつの大きな目的に、
「親元を離れる」というものがあります。
親との距離が近すぎると、ほぼずっと一緒にいるために、
いろいろと介入してしまうからです。
距離感をあまり考えずに介入しすぎてしまうと、
依存関係が生まれ、自立の妨げになってしまいます。
つまり、過剰な介入をすると、子ども自身が成長しません。
一方、わたしたちホームのスタッフは「他人」なので、
ある程度の距離感を持って対応できます。
これが、ひとつの重要なポイントと言えるでしょう。
ゆっくりではありますが、グループホームで過ごすことで、
変化が見られることはよくあることなのです。