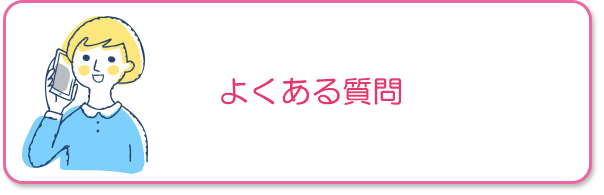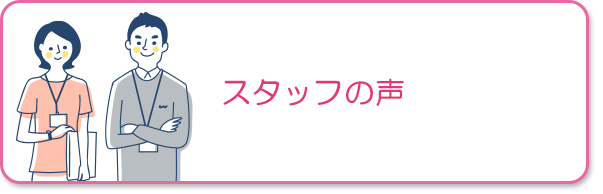~障がい者グループホーム~
「違い」を認める社会をつくる
ネクストハピネス
『はじめての障がい者グループホーム』(BLA出版)Kindle版
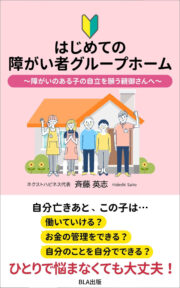
障がいのある子の自立を願う親御さんへ
グループホームの基本的な知識や入居者の人間模様、
障がいのある人たちとの向き合い方などを、マンガを交えてわかりやすく解説しています。
『障がいを持つ子の親が70歳までに準備するべき相続対策』(BLA出版)Kindle版
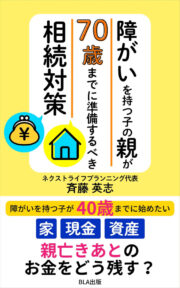
障がいのある子を持つ親御様は、「親亡きあと」のお子様の生活や、ほかの子たちへの負担に不安を抱えていながら、どこから手をつけていいのかわからないのではないでしょうか。
まずは「はじめの一歩」を知ることが、大いなる安心につながるのです。
本書では、相続や不動産のコンサルタントであり、自ら障がい者グループホームを4棟運営する著者が、子が自立できる環境の整備や相続の基本をわかりやすく解説しています。
ひとりで悩み、抱え込まなくても大丈夫です。
まずは、『「障がいのある子を持つ親」のチェックリスト』であなたの現在地を知ったうえで、本書を読み進めましょう。
親亡き後のことを考えるとき、子どもの家族関係の整理や、今後の人生設計など、
さまざまな不安や悩みを抱えることになります。
さらに子どもへの遺産相続や生活場所、生活費、介護、就労など、さまざまな問題が発生します。
「親亡き後の対策・サポート室」では、障がい者福祉のプロ(障がい者グループホーム)が中心となり、相続対策の専門家、不動産の専門家、お金の専門家(ファイナンシャルプランナー)がそれぞれの経験・強みを活かし 親亡き後の問題解決に向けてトータルサポートいたします。
さらに子どもへの遺産相続や生活場所、生活費、介護、就労など、さまざまな問題が発生します。
「親亡き後の対策・サポート室」では、障がい者福祉のプロ(障がい者グループホーム)が中心となり、相続対策の専門家、不動産の専門家、お金の専門家(ファイナンシャルプランナー)がそれぞれの経験・強みを活かし 親亡き後の問題解決に向けてトータルサポートいたします。
お知らせ
わたしたちについて
将来的には打ち込みたいことを見つけ、
その支援・応援をさせていただくようなグループホームでありたい。
その支援・応援をさせていただくようなグループホームでありたい。
障がいのなかでも、精神疾患や発達障害は、まわりの人から理解されにくいのではないでしょうか。
わたしたちは、このような障害をお持ちの方々が地域に受け入れられるような橋渡しや、
ご家族・ご本人へのサポートをしていきたいと思っています。
わたしたちは、このような障害をお持ちの方々が地域に受け入れられるような橋渡しや、
ご家族・ご本人へのサポートをしていきたいと思っています。
障がい者グループホームについて
障がい者グループホームとは。
お子さまの将来に悩む親御さまのために、
「障がい者グループホーム」という施設があります。
障がい者グループホームとは、障害のある人が数人で、
世話人などから生活や健康管理面のサポートを受けつつ、共同生活を営む住宅です。
基本的に18歳から64歳までの方が、この施設を利用できます。
「障がい者グループホーム」という施設があります。
障がい者グループホームとは、障害のある人が数人で、
世話人などから生活や健康管理面のサポートを受けつつ、共同生活を営む住宅です。
基本的に18歳から64歳までの方が、この施設を利用できます。
施設紹介
ネクストハピネスの障がい者グループホームは、千葉県千葉市、八千代市に合計4ヵ所あります。
採用情報
コラム

5つのチェックリストから現状を確認しよう(2)
●地域・社会と関わる機会を持っていますか? 前回のコラムでは、「生活力」についてご紹介しました。 今回は「地域・社会との関わり」について見てみましょう。 これから紹介するチェック項目は、 「障 […]

5つのチェックリストから現状を確認しよう(1)
●まずは、子どもやまわりの現状を知る 「発達障がい」「精神障がい」「知的障がい」は、 個人によってその程度が異なります。 適切なサポートを見つけるために、 まずお子さんとご家族の「親亡きあとの対策」の現状を […]

親亡きあとも、子どもが安心して暮らせる環境を整えよう
●「自立」を目指すことが、家族みんなの安心につながる 親が元気なうちは、障がいのある子どもの通院や 日常生活を支えることも可能でしょう。 でも、年齢を重ねるにつれて、 急な体調変化や対応が難しくなる場面は […]
このような“受け皿”となる施設があったら、
いいと思いませんか?
いいと思いませんか?
● 子どもの自立への第一歩となってくれる
● 高齢になった自分たちに代わって子どもをサポートしてくれる
● 薬の服用や金銭の管理をサポートしてくれる
● 高齢になった自分たちに代わって子どもをサポートしてくれる
● 薬の服用や金銭の管理をサポートしてくれる
まずはお問い合わせください
メールでお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ